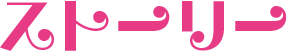その4)第1話「マッチ売りの少女」収録現場での葛藤

タイトルやコンセプトに音楽、制作方法に至るまで、プロデューサー・古坂大魔王と谷口崇監督のこだわりが凝縮された作品『ピコ太郎のララバイラーラバイ』。最終回である制作レポートその4では、実際にピコ太郎が収録を行った現場の模様についてお伝えしていきたい。
スタジオに入ったピコ太郎は、谷口が描いた、1つの物話につき1枚の白黒絵を手渡される。そこに描かれているのは、「シンデレラ」「マッチ売りの少女」「赤ずきん」など誰もが知るおとぎ話の世界の中に、時には自然に・時には不自然に入り込んだピコ太郎の姿。1回の収録につき8枚(8話)ほど準備されるラフを片手に、どの“おとぎ話”を基軸に物語を展開していくかを精査するピコ太郎。しかしファーストインプレッションに最も重きを置く本作、思考もそこそこに収録ブースに入り、即興で世界を広げていった。
一見順調に見える収録の中でも、物語の“オチ”の部分に苦労したものもあるとか。それもそのはず、なんせそこで形作られるストーリーには何の指針もないのだ。良い終着点にたどり着くことができず、結末に至るまで予想以上の時間を費やしてしまったものもあるという。そんなピコ太郎に、古坂は「変な設定を急に耳元でつぶやいたり、意味不明なセリフを入れ込んだりと、いろいろと無茶ぶりしました。」と語る。
ネタを撮り終わった後のピコ太郎の疲労を癒すのも古坂の仕事で、飴をあげたり、おもちゃのヘビで笑わせたりしながら、ピコ太郎のモチベーション維持に奮闘していたようだ。こうして作られた第1話「マッチ売りの少女」は、ピコ太郎の緊張感や息づかいなどが反映された、唯一無二の作品へと仕上がった。(※現在無料公開中)
いずれは、英語や中国語やロシア語など、様々な国の字幕を入れて世界中にこの作品を広め、短編アニメとしてアカデミー賞を狙いたいと、野望を語る古坂。
今後の展開、その全てに期待が高まる。