応募に関するご相談
どこの事務所が自分に合うのか分からない。
そんな時は・・
まずは、LINEでご相談
豊富な業界情報をもとに、あなたにあった活動先をご案内します。


「歌い手になるには、何から始めればいい?」 そう思いながらも「機材が必要?」「どこで投稿すればいい?」と悩んでいませんか?
実は、歌い手活動はスマホ1台あれば、誰でも始められます。
しかし、ただ歌を投稿するだけでは、多くの人に聴いてもらうのは難しいのも事実です。人気のある歌い手は、選曲や歌い方の工夫、SNSの活用などを駆使しながら、少しずつファンを増やしています。
本記事では、歌い手になるための具体的な方法や初期費用、収入の仕組みを詳しく解説します。 これから歌い手活動を始めたい方に向けて、必要なポイントをわかりやすくまとめました。
ぜひ最後まで読んで、あなたに合った方法を見つけてみてください。
目次

歌い手とは、主に「歌ってみた動画」や「オリジナル楽曲」を投稿し、オンラインで活動するアーティストのことです。プロ・アマを問わず、SNSや動画配信プラットフォームを活用して、自分の歌声を発信できます。
近年、YouTubeやTikTok、ニコニコ動画などのプラットフォームが発展し、個人でも簡単に音楽活動を始められるようになりました。プロの歌手とは異なり、レコード会社との契約がなくても活動できるため、趣味からスタートする人も多くいます。
歌い手の活動内容は、大きく分けて3つあります。
|
歌ってみた(カバー曲の投稿) |
|
|
オリジナル楽曲の制作・発表 |
|
|
ライブ配信(生歌・ファンとの交流) |
|
歌い手は、動画投稿・オリジナル楽曲・ライブ配信など、多様なスタイルで活動できます。プロとアマの垣根が低く、誰でも気軽に始められるのが魅力です。まずは、自分に合った方法で歌を発信してみましょう。

歌い手として活動を始めるには、最低限の準備が必要です。とはいえ、必ずしも高額な機材をそろえる必要はなく、スマホ1台でもスタートできます。
本格的に活動する場合は、音質や編集のクオリティを向上させるための機材をそろえるとよいでしょう。
どのプラットフォームで活動するかによって、戦略も変わります。YouTubeやニコニコ動画、TikTokなど、それぞれの特徴を理解し、自分に合った場所を選ぶことが大切です。
ここでは、歌い手として活動を始めるために必要な機材や、最適なプラットフォームについて詳しく解説します。
歌い手活動は、スマホ1台でも気軽に始められます。特に最近は、スマホのマイク性能や録音アプリの進化により、高品質な音声を手軽に録音できるようになっています。
編集や投稿もスマホだけで完結するため、初期費用をかけずにスタートできるのが大きなメリットです。
スマホだけで始めるなら、以下のような方法があります。
録音のクオリティを上げるには、以下のようなポイントを意識しましょう。
高価な機材がなくても、スマホだけで歌い手活動を始めることは十分に可能です。まずは無料のアプリを活用して、気軽に「歌ってみた」を録音・投稿してみましょう。
スマホだけでも歌い手活動を始められますが、音質や編集のクオリティを向上させたいなら、専用の機材をそろえるのがおすすめです。
ただし、こだわり始めると必要な機材が増え、費用もかかります。「本当に続けたい」と思えたタイミングで、少しずつ環境を整えていくのが良いでしょう。
本格的に活動したいなら以下のような機材を検討してみましょう。
|
マイク |
スマホ内蔵マイクよりも圧倒的に音質が向上 手軽に使える 「USBマイク(例:Blue Yeti、AT2020USB+)」 ならPCに直接接続可能 高音質を求めるなら XLRマイク+オーディオインターフェース(例:SHURE SM7B+YAMAHA AG03) を導入するとプロ仕様に |
|
オーディオインターフェース |
XLRマイクは直接PCにつなげないため、インターフェースが必要 |
|
編集ソフト |
録音した歌声にエフェクトをかけたり、ノイズを除去したりするための編集ソフト 無料ソフトなら「Audacity」 がシンプルで使いやすい |
社会人やバイトをしている学生なら、最初からある程度そろえるのもアリですが、お金がない学生でも問題ありません。スマホ1台で活動をスタートし、「本当に楽しい! もっとやりたい!」と思ったら機材をそろえていけば十分です。
まずは身近な環境で始めて、続ける中で必要なものを見極めていきましょう。
歌い手として活動するなら、どのプラットフォームを選ぶ必要があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったプラットフォームを選べば、より多くの人に歌を届けやすくなります。
|
YouTube |
歌い手の活動場所として最も人気が高いプラットフォーム 圧倒的な視聴者数 長尺の動画も投稿可能 人気の歌い手が多く、新規参入は工夫が必要 収益化の条件が厳しい |
|
ニコニコ動画 |
ボーカロイド楽曲や「歌ってみた」文化が根付いているプラットフォーム リアルタイムで視聴者の反応が見える ボカロ曲を歌いたい人には特におすすめ YouTubeに比べると視聴者が少ない プレミアム会員でないと画質や容量の制限がある |
|
TikTok |
ショート動画がメインのプラットフォーム 音楽との相性が良く、バズることで一気に知名度を上げられる 拡散力が圧倒的 編集もアプリ内で完結 短尺動画がメイン アルゴリズム次第で再生数が変わる |
|
ツイキャス |
生歌を披露したり、ファンとリアルタイムで交流したい人におすすめ 気軽にライブ配信ができる コメントを通じて直接やりとりが可能 投げ銭(アイテム課金)で収益化できる 配信を見てもらうには、ある程度のファンが必要 |
どのプラットフォームか迷ったら、以下のポイントを参考にしてください。
|
どのプラットフォームを選ぶべき? |
|
それぞれのプラットフォームで特徴が異なるため、自分のスタイルに合った場所を選びましょう。複数のプラットフォームを組み合わせて活動するのも一つの戦略です。
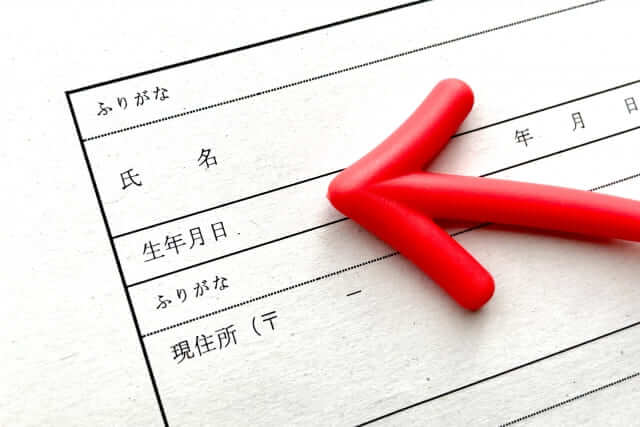
歌い手になるのに、年齢制限はありません。小学生から社会人まで、幅広い世代の人が活動しています。ただし、年齢によって気をつけるべきポイントや、活動のしやすさには違いがあります。
ここでは、年齢ごとのメリット・注意点を整理しながら、どの世代でも歌い手活動を楽しめるポイントを解説します。
小学生や中学生でも、歌い手活動は十分に可能です。実際に、若い世代から活動を始めて人気を集めている歌い手もいます。ただし、年齢が低いほど注意すべきポイントも多いため、安全に楽しく活動するための準備が大切です。
具体的には、以下のようなポイントに注意しましょう。
|
保護者の許可を得ることが必須 |
|
|
プラットフォームの年齢制限に注意 |
|
|
声変わりの影響 |
|
|
安全対策 |
|
年齢に関係なく、歌い手になることは可能です。ただし、ネット上での活動にはリスクもあるため、保護者と相談しながら安全に進めることが大切です。
まずはスマホやタブレットを使って、「歌ってみた」を気軽に投稿してみましょう。
10代~20代は、歌い手活動を始めるのに最適な年代です。SNSや動画配信プラットフォームとの親和性が高く、新しいトレンドをキャッチしやすいのが強みといえます。
若いうちから活動を続けることで、知名度を上げやすく、長期的に成長していけるメリットもあります。
10代~20代の歌い手の強みには、以下のようなポイントが挙げられます。
|
SNSを活用した発信力が高い |
|
|
新しい音楽スタイルに柔軟に対応できる |
|
|
同世代のファンがつきやすい |
|
Adoさんは、10代の頃から「歌ってみた」を投稿し、圧倒的な歌唱力で注目を集めました。その後、メジャーデビューし、数々のヒット曲を生み出しました。
このように、10代から活動を始めることで、大きなチャンスをつかめる可能性があります。
若い世代は、SNSの活用や新しい音楽トレンドへの適応力が強みです。まずは好きな曲の「歌ってみた」から始めて、自分の個性を発信してみましょう。
30代以上でも、歌い手として活動することは十分に可能です。実際に、社会人や家庭を持つ人でも歌い手として活躍している例は多く、年齢を重ねたからこそ出せる歌声の魅力や表現力を武器にできるのが強みといえます。
10代や20代と比べると経済的な余裕があることが多く、機材や環境を整えやすいのもメリットの一つです。
30代以上の歌い手の強みには、以下のようなポイントがあります。
|
表現力や経験を活かした歌唱ができる |
|
|
経済的な余裕があるため、機材をそろえやすい |
|
|
安定した活動を続けやすい |
|
すとぷりのメンバーであるさとみさんは、1993年生まれ(2025年時点で32歳)ですが、現在も精力的に活動を続けています。年齢を重ねても、ファンを魅了し続けられることを証明しており、歌い手は年齢に関係なく挑戦できる職業の一つといえるでしょう。
30代以上だからといって、歌い手になれないわけではありません。むしろ、表現力や経済力を活かせるメリットがあり、落ち着いた雰囲気や大人の魅力を武器にもできます。自分のスタイルを見つけて、歌い手活動を楽しんでみましょう。

歌い手として活動を始めたからには、できるだけ多くの人に自分の歌を聴いてもらいたいですよね。しかし、ただ歌を投稿するだけでは、なかなか注目を集めるのは難しいのが現実です。
ここでは、歌い手として人気を集めるための具体的な方法を紹介します。
人気のある歌い手になるためには「ただ上手く歌う」だけではなく、自分ならではの個性を出すことが大切です。特に、選曲や歌い方にオリジナリティを加えることで、リスナーの印象に残りやすくなります。
歌い手は多くの人が挑戦しているジャンルです。そのため、ただ流行りの曲を歌うだけでは埋もれてしまいがちです。リスナーに「この人の歌、また聴きたい!」と思わせるには、選曲や歌い方で独自の魅力を出さなければなりません。
個性を出すためには、以下のようなポイントを意識してみましょう。
|
自分の声質や表現に合った曲を選ぶ |
低音が得意ならクールな楽曲、高音が強みなら感情を込めやすいバラードなど、歌のジャンルを工夫する |
|
意外性のある選曲をする |
男性が女性ボーカルの曲を歌う、アップテンポの曲をしっとりアレンジするなど、独自のスタイルを取り入れる |
|
フェイク(音の装飾)や発声の工夫を加える |
Adoさんのように、曲ごとに歌い方を変えてみるのも効果的 |
選曲や歌い方にこだわることで、他の歌い手と差をつけられます。 ただ流行を追うのではなく、自分に合った楽曲を見つけ、自分らしい歌い方を磨いていきましょう。
歌い手として活動するなら、ソロだけではなくグループでの活動も選択肢の一つです。 近年、ユニットやグループでの歌い手活動が増えており、個人とは違った魅力を発揮できます。
ソロ活動は自由度が高いですが、その分、すべてを自分でやる必要があります。一方、グループで活動すると、お互いに支え合いながら活動できるのがメリットの一つです。特に、ファン層を広げやすく、SNSでの拡散力が高まるのも強みです。
グループ活動のメリットには、以下のようなな点が挙げられます。
|
役割分担ができる |
歌・MIX・動画編集など、それぞれ得意な分野を活かせる |
|
コラボの相乗効果がある |
お互いのリスナーが流入し、ファン層が広がる |
|
モチベーションを維持しやすい |
一緒に目標を設定し、励まし合いながら成長できる |
「すとぷり」や「浦島坂田船」など、ユニットとして活動し、成功しているグループが増えています。個人活動では難しい大規模なライブや企画も、グループなら実現しやすくなるでしょう。
グループ活動を取り入れることで、より楽しく、長く歌い手活動を続けられます。 まずは、気の合う仲間とコラボを試しながら、ユニットやグループ活動の可能性を探ってみるのも良いでしょう。
歌い手活動を成功させるには、SNSの活用が欠かせません。 いくら素晴らしい歌を投稿しても、誰にも知られなければ再生数は伸びません。SNSを上手に使えば、より多くの人に自分の歌を届けられるでしょう。
現在、音楽の発信はYouTubeやニコニコ動画だけではなく、SNSを通じて拡散されることがほとんどです。特に、TikTokやX(旧Twitter)などはバズることで一気に知名度を上げることができるため、歌い手にとって大きなチャンスとなります。
効果的なSNS活用例は、以下のとおりです。
|
X(旧Twitter)で情報発信 |
|
|
TikTokでショート動画を投稿 |
|
|
YouTubeショートやInstagramリールも活用 |
|
SNSを活用すれば、自分の活動を知ってもらうだけではなく、リスナーとの距離を縮めることもできます。投稿へのリアクションや、リスナーのコメントに返信すれば、より応援してもらいやすくなるでしょう。
歌い手としての活動を広げるためには、コラボが効果的です。 ソロ活動だけでは届けられない層にも、自分の歌を知ってもらうチャンスになります。
特に、他の歌い手やクリエイターとコラボすれば、お互いのリスナーを共有し、ファンを増やしやすくなるでしょう。
1人で活動していると、どうしてもファンの拡大には限界があります。しかし、コラボすれば、新しいリスナーに自分の存在を知ってもらう機会が増えるため、自然と認知度が上がります。
異なる歌声や表現が組み合わさることで、1人では出せない魅力を生み出すことも可能です。
コラボの種類とメリットには、以下のようなものがあります。
|
デュエットやハモリ系コラボ |
|
|
歌い手×MIX師・動画師とのコラボ |
|
|
イベントや配信でのコラボ |
|
1人での活動にこだわらず、他の歌い手やクリエイターと協力すれば、新しい可能性が広がります。仲の良い歌い手や、自分と相性の良さそうな人とコラボを企画して、積極的に挑戦してみましょう。

歌い手活動は、スマホ1台でも始められますが、本格的に取り組む場合は機材や編集ソフトなどの費用がかかります。
どこまでお金をかけるかは人それぞれですが、機材や環境を整えることで音質や動画のクオリティが向上し、より多くの人に聴いてもらいやすくなります。
また、歌い手活動で収益を得る方法もいくつかあります。 ここでは、歌い手活動にかかる費用の目安と、収益を得る方法を詳しく解説します。
歌い手活動は、スマホ1台でも始められるため、初期費用ゼロでもスタート可能です。 特に最近は、スマホのマイク性能や録音アプリが向上しており、編集や投稿もスマホだけで完結できます。
初期費用をかけずに始めるには、以下のようなアプリや機能を活用しましょう。
しかし、より高音質で歌を届けたい場合や、本格的に活動したい場合は、機材をそろえるとクオリティが格段にアップします。
具体的には、以下のような機材の導入を検討しましょう。
初期費用はゼロでもOKですが、より高音質・高クオリティを目指すなら、少しずつ機材をそろえるのもアリです。 まずは手軽に始めて「もっと本格的にやりたい!」と思ったら、必要なものを買い足していくのが良いでしょう。
歌い手として活動しながら収益を得る方法はいくつかあります。 収益化の手段を知っておくことで、好きなことを続けながら収入を得るチャンスが広がります。
活動スタイルによって収益源も異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
具体的には、以下のような方法があります。
|
YouTubeなどの広告収入 |
|
|
投げ銭・ライブ配信の収益 |
|
|
グッズ販売・CD販売 |
|
|
ファンクラブ・コミュニティ運営 |
|
|
企業案件やタイアップ |
|
歌い手の収益化にはさまざまな方法があり、1つの手段にこだわる必要はありません。 自分の活動スタイルに合った方法を選び、収益を得ながら楽しく活動を続けましょう。
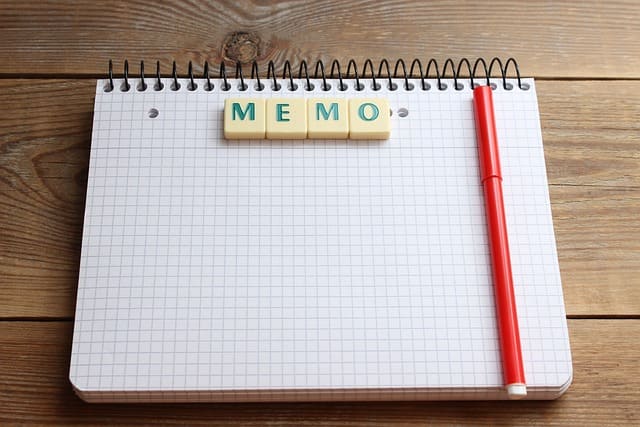
歌い手活動は、始めることよりも「続けること」が難しいといわれています。最初は楽しくても、再生数が伸び悩んだり、モチベーションが下がったりして、途中でやめてしまう人も少なくありません。
ここでは、歌い手活動を長く楽しみながら続けるための秘訣を紹介します。
歌い手活動を続ける上で、一緒に頑張れる仲間の存在はとても大切です。 一人で黙々と活動もできますが、仲間がいることでモチベーションを維持しやすくなり、楽しさも倍増するでしょう。
仲間を見つける方法には、以下のようなものがあります。
一緒に頑張れる仲間がいれば、活動のモチベーションを維持しやすく、困ったときも支え合え、歌い手としての成長にもつながります。最初は一人でも、少しずつ交流の輪を広げていきましょう。
歌い手活動を続ける上で、仲間やリスナーとの良好な関係を築くことはとても大切です。 コラボやSNSでの交流が増えると、自然とさまざまな人と関わる機会が増えます。
しかし、ちょっとしたトラブルや誤解が原因で関係がギクシャクしてしまうこともあるため、円滑なコミュニケーションを心がけましょう。
歌い手活動で大切な礼儀やマナーは、以下のとおりです。
「歌い手」としての活動は一人でもできますが、仲間やリスナーとのつながりがあることで、より楽しく、長く続けることができます。 良好な人間関係を築くためにも、基本的なマナーを大切にしながら活動していきましょう。
歌い手活動は、続けることが何よりも大切です。 最初は楽しくても、再生数が伸び悩んだり、忙しくなったりすると、モチベーションが下がってしまうこともあります。しかし、無理なく続けるコツを知っておけば、長く楽しく活動を続けられます。
具体的には以下のポイントを意識しましょう。
|
①完璧を求めすぎない |
|
|
②自分のペースで続ける |
|
|
③小さな目標を設定する |
|
|
④楽しむことを忘れない |
|
長く活動を続けるためには「完璧を求めすぎず、自分のペースで楽しむこと」が大切です。 焦らず、無理なく、自分らしいスタイルで歌い手活動を続けていきましょう。

歌い手活動は楽しい反面、気をつけるべきポイントもあります。 知らず知らずのうちに問題を引き起こしてしまうと、せっかくの活動が続けられなくなることもあるため、正しい知識を身につけることが大切です。
ルールを守らずに投稿すると削除やアカウント停止のリスクもあります。
ここでは、歌い手として安心して活動を続けるために、注意すべきポイントを解説します。
「歌ってみた」動画や音源を投稿する際、著作権のルールを守ることはとても大切です。 ルールを知らずに投稿してしまうと、動画の削除やアカウントの停止、場合によっては法的なトラブルにつながることもあります。
具体的には、投稿する際は、以下の点に気をつけましょう。
|
原曲の使用許可を確認する |
|
|
公式のオフボーカル音源を利用する |
|
|
収益化のルールを守る |
|
著作権のルールを守ることで、安心して活動を続けることができます。 投稿する前に使用許可の有無や、収益化のルールをしっかり確認し、安全に歌い手活動を楽しみましょう。
歌い手として活動するなら、SNSや動画投稿を通じて多くの人と関わります。 その分、誹謗中傷や炎上のリスクもゼロではありません。何気ない発言や行動が問題視されることもあるため、慎重な立ち回りが大切です。
具体的には、以下のような点に気をつけましょう。
|
身バレを防ぐ |
|
|
SNSの発言に気をつける |
|
|
誹謗中傷を受けたときの対応 |
|
|
配信やコメント管理を徹底する |
|
炎上や誹謗中傷は、人気が出るほど避けられないリスクの一つです。 しかし、事前に対策をしておけば、自分の身を守りながら安心して歌い手活動を続けることができます。
無理にすべてを受け止めるのではなく、適切に対処しながら活動を楽しんでいきましょう。
歌い手は、誰でも挑戦できる活動です。スマホ1台からでも始められ、本格的にやるなら機材をそろえてクオリティを高めることもできます。続けていくことで、自分の個性を活かした歌い方やスタイルが確立し、ファンも増えていくでしょう。
しかし、人気の歌い手になるには、継続的な努力や工夫が必要です。SNSの活用やコラボを積極的に行い、リスナーとの関係を大切にしていきましょう。
著作権のルールを守り、誹謗中傷などのトラブルから身を守る意識も欠かせません。
まずは、できることから行動してみましょう。
「やってみたい!」と思った今が、歌い手になるスタートです。 自分のペースで楽しみながら、歌を届ける活動を始めてみましょう!